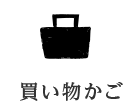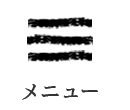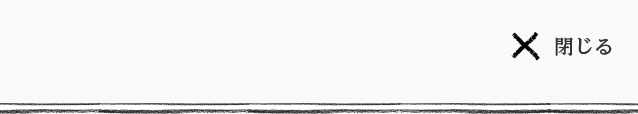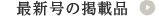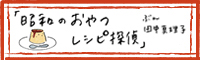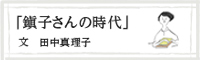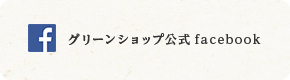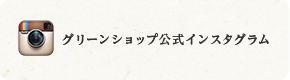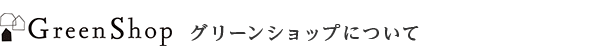『暮しの手帖』は昭和20年、敗戦間もない東京で胎動しはじめます。「家族を幸せにするために収入を得たい。そのために女の自分ができること、したいことは何なのか?」。鎭子さんが思い至った結論は「本や雑誌をつくって出版すること」でした。
戦争中満足に勉強できなかった経験から「自分と同じように、もっといろいろなことを知りたいと思っている女の人がいるはず、そんな人に役立つ本や雑誌をつくれば売れるに違いない」と考えたのです。
紹介してくださる方がいて花森(安治)さんと出会い、その思いは大きく動いていくのですが、最初に鎭子さんのひらめきに賛同したのは家族。母の久子さんと妹の晴子(はるこ・次女)さん、芳子(よしこ・三女)さんでした。

大橋家三姉妹。 左から晴子さん、芳子さん、鎭子さん。 1950年代、品川の自宅の居間で撮影。
鎭子さんと芳子さんはその生涯を独身で通し『暮しの手帖』の編集者として活躍する一方、晴子さんは結婚、子育てで一線を退きます。そのためあまり知られていないのですが、創業時はずいぶん尽力したようです。当時晴子さんは丸の内の保険会社に勤務。その働きぶりを信頼した方が資金を貸してくださり、また会社が終わると銀座のビルを一軒一軒訪ねて編集室を置くための空き部屋を探して回ったのも晴子さんでした。
先日現在94歳になる晴子さんをご自宅に訪ねました。晴子さんは母・久子さんと三姉妹が生涯いっしょに暮らした品川の家に今も住んでいらっしゃいます。戦後まもなく建てられ、昭和28年、昭和33年と2度の改築を経た家はほぼ当時のまま。『暮しの手帖』の撮影にも使われていたキッチンやリビングはなつかしいけれどとてもモダンなたたずまいでした。
姉の鎭子さんを平成25年に、妹の芳子さんを平成26年に亡くされた晴子さんは「さびしいわね」と話され、からだのうごきはゆーっくりです。でもちょうど届いた『暮しの手帖』の最新号に目を通し「今回はピカイチね。知らないことがいろいろ書いてあるもの」と一言。きっとずっと新刊が出るたびにこうしてしっかりと見てこられたのだろうと思いました。
晴子さんは私たち来客のためにお茶菓子の心配をし、身支度も整えておいででした。でも家の中なのに手袋をしています。気になってそっとうかがったところ「手入れをしていなくてはずかしいから」とおっしゃいました。でも手袋をはずした手はとてもやわらかくてきれいだったのです。失礼な言い方かもしれませんが、若々しい。それを見て思い出したのは鎭子さんの手のことでした。