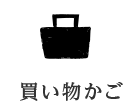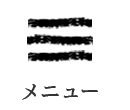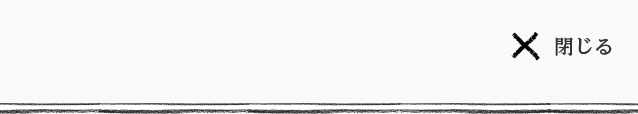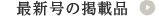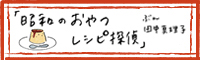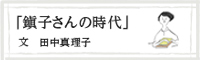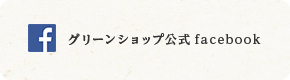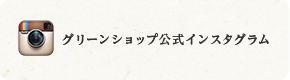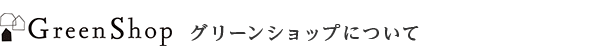昭 和のビスコッティ?
「昭和のおやつ レシピ探偵」第4話は、「干柿のピーナッツバー」を再現してみることにしました。
『暮しの手帖』のバックナンバーには探偵を引きつけてやまないおやつが山盛りなのですが、なかでもそそられるのは写真やネーミングからイメージがどんどん広がったり、作った方のことをもっと知りたいと思うときです。昭和29年発行の『34号』で紹介されていた「干柿のピーナッツバー」はまず写真と名前にぐっときました。完成したおやつはビスコッティ風。最近よく見かけて買うことも多いし、国産のドライフルーツを使っているのも嬉しいではありませんか!
て いねいな写真とレシピ
さっそくレシピを読み始めました。いつものように、この当時の1カップは1合180cc、茶匙1杯は6cc。分量は置き換えが必要なものの、写真も文章もとても親切でわかりやすく、料理は一般主婦レベルの探偵にはとても助かります。「干柿はねばつてお互いにくつつきやすいから、しやもじではなれるようにかきまぜます」・「(ピーナッツを入れると)ちようどつきたてのお餅のような固さになります」などなど。
この当時としては珍しく、天火(オーブン)を使っていますが、今回は使い慣れたオーブントースターで作ってみました。ワット設定があり、300ワットで予熱しておくとちょうど中火(180℃)に。これはうまくいきました。
立 派な干柿
悩んだのは干柿でした。材料には、大きめの5・6個とありますが、柿を刻む鎭子さんの手と比べるとかなり立派です。今ならブランド干柿と推測されますが、当時の干柿はどんな存在だったのでしょう?
昭和30年東北生まれの探偵にとって干柿は冬のこたつの友。軒先に吊るしている家がたくさんありました。ひと回り上の知人に聞いても同じ答えで、彼は「そうそう、焼いて食べるとおいしかった」と言います。『暮しの手帖』編集部でこのおやつを取り上げた理由も、材料としてポピュラーだったからだと思うのです。それから60年後の今、干柿は高級品化と生産量の減少傾向にあります。ちょっと感傷にひたりつつ、でも天然の甘みがこれからも引き継がれる事を願いつつ、ねばる干柿を刻みました。

型は使わず、天板に流し、オーブントースターで焼きました。今回の材料では、約15×25㎝が2回分ありました。1枚はそのまま、もう1枚は冷めてから切りわけ、側面を並べて低温で20分ほど焼いて乾燥させ、ビスコッティ風にしました。柿の風味は乾燥させない方が俄然生きています。
な つかしい食感
「バー」は、干柿とピーナッツと卵の風味が伝わるやさしい味の素朴なおやつに焼き上がり、試食してもらった友人たちにも好評でした。でも食感が予想とは違っていたのです。さくっとビスコッティのつもりが、しっとりしている。ちょっと湿り気があるのです。分量を間違えたかな? 「いや、これでいいと思う。『黒棒』みたいなこの噛みごたえが、まさに昭和のおやつなんじゃないかな」とお菓子作りに詳しいひと回り下の友人。なるほど確かに「味噌パン」や「丸ぼうろ」とも近い感じです。先入観は禁物。鎭子さんが食べたのは、この焼き上がりでよかったのではないかと思い直しました。
今回ひとつ心残りがあります。レシピを指導したミルドレッド・B・ダニエルスさんのことがわからないままでした。第1話・第2話の門倉國彦さん、第3話のサト・ナガセさんのことは少しご紹介できたのですが。もしご存知の方がいらっしゃればぜひご一報いただければと思います。 「干柿を使ったピーナッツバー」は「3つのお菓子」と題された特集のひとつで、「イギリスふうのタッフィ」・「チョコレート クッキィ」とともに掲載されています。最後にこのふたつのレシピもご紹介いたします。